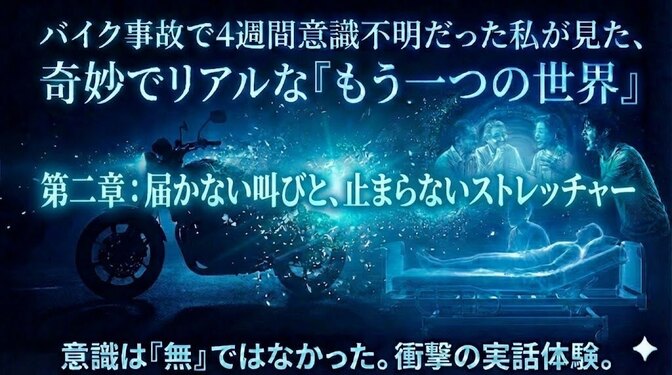第二章:届かない叫びと、止まらないストレッチャー
目を覚ますたび、そこは微妙に、しかし決定的に違う世界だった。 私は、終わりのない夢の回廊を彷徨い続けていた。
「夢」という言葉から連想されるような、輪郭が曖昧で、セピア色に霞んだような世界ではない。そこは、恐ろしいほどに鮮明で、現実以上に「色彩」が暴走した世界だった。
視界を埋め尽くす極彩色の光。窓から差し込む陽光は、まるで最新鋭のCG映像のように粒子の一つひとつが過剰に書き込まれ、プリズムを通したようにギラギラと輝いている。赤は血管を流れる血よりも毒々しく、青は深海のように目が痛くなるほど深く、黄色は警告色のように神経を逆撫でして明滅する。
空間そのものも、どこか狂っていた。 部屋の四隅を見ても、直角であるはずの線がぐにゃりと歪んで交わっている。天井は不自然に高く、あるいは低く、遠近感がデタラメな抽象画の中に閉じ込められたようだ。 壁にかかった時計を見上げると、文字盤の数字が水あめのように溶け出し、渦を巻いていて時間は読み取れない。ここでは「時間」という概念自体が意味をなさず、ただ永遠に引き伸ばされた「今」があるだけだった。
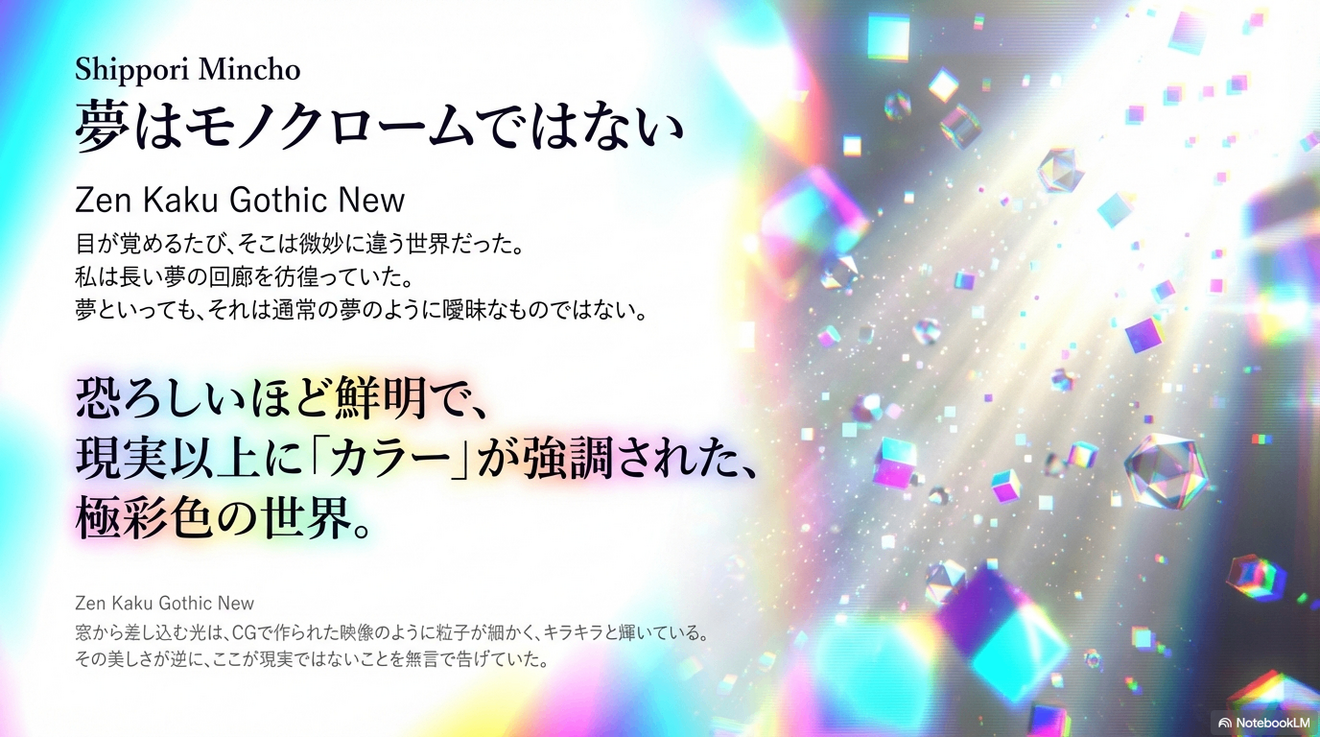
「ポタ、ポタ……」 頭のすぐ横で、規則的な水音がする。点滴だ。 その透明な液体がチューブを通って私の腕に流れ込んでくるたび、舌の裏にはアルミホイルを噛んだような不快な金属味が広がり、血管の中を氷水が這い上がってくるような悪寒が走る。 この世界では、痛みすらも鮮やかな電気信号のようなノイズとして変換されていた。
ある時、ふと意識が浮上すると、母がベッドの脇にあるパイプ椅子に座っていた。 見慣れた姿だが、その顔は急激に歳を重ねたかのようにやつれ、皮膚は土気色にくすんでいる。頬はこけ、瞬きすら惜しむようにじっと私を見つめていた。 私は張り詰めていた糸が切れたように安堵し、ひび割れて乾いた喉から声を絞り出した。
「母さん! 母さん、俺はここだよ! 目が覚めたんだ!」
しかし、母は反応しない。 彼女の瞳は、確かに私の顔に向けられている。だが、焦点が合っていない。私の顔の皮膚を通り越し、その奥にある頭蓋骨、あるいはもっと後ろの「虚空」を凝視しているようだった。 その瞳には、私の姿は映っていない。ただの肉の塊を見ているような、生気のない目。
「……なんで……どうして、あの子が……」
母の唇から、掠れた独り言が漏れる。それは会話ではなく、壊れたレコードのように繰り返される絶望のつぶやきだった。
「……代わってあげたい……私が……」
「ねえ、母さんってば!」 私は焦燥に駆られてさらに声を張り上げ、ベッドの柵を乗り越えるようにして手を伸ばす。だが、私の指先が母の肩に触れようとした瞬間、本能的な恐怖がよぎる。手は霞を掴むように、母の体をすり抜けてしまうのではないかという予感。 実際には触れることさえできなかった。私の絶叫は、まるで分厚い防音ガラスの中に閉じ込められたかのように、こちらの世界で空しく反響するだけで、あちら側の母には一切届かない。 そこにあるのは、1センチの距離に横たわる、数万光年の圧倒的な断絶だった。
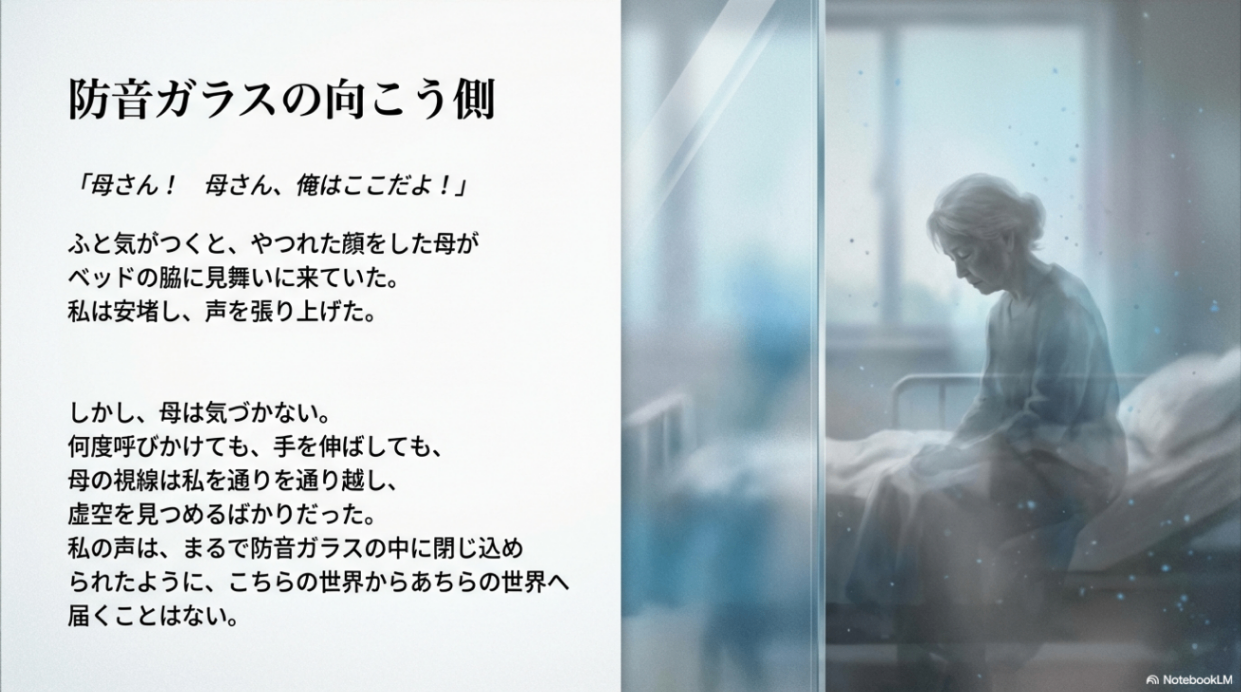
またある時、瞬きをした瞬間に場面が唐突に切り替わっていた。 違和感を覚えて横を見ると、私のベッドの隣に、遠方に住んでいるはずの従兄妹が寝ているのだ。反対側のベッドにも、また別の親戚が横たわっている。 驚いて見渡せば、病室の壁は遥か彼方まで伸び、そこには無数のベッドが並んでいた。病室全体がまるで親戚一同を収容する巨大なドミトリー、あるいは野戦病院のような異様な空間に変貌していた。
「おい、なんでお前らがここにいるんだ? 起きろよ」
声をかけてもその声は届かない。彼らはただ静かに、不気味なほど規則正しいリズムで、シンクロした寝息を立てている。ヒュー、ヒュー、という呼吸音が、まるで一つの巨大な有機体の鼓動のように響く。その寝顔には生気がなく、肌はプラスチックのように滑らかで、まるで彼らもまた、魂の抜け殻だけをここに置いていったかのようだった。
場面は脈絡なく切り替わる。共通しているのは、「誰にも声が届かない」という絶対的な孤独と、真空のような静寂だけ。 そこは、生者の世界と死者の世界が混ざり合い、しかし決して交わることのない中間の領域――「幽界」としか呼びようのない場所だった。
そんな極彩色の迷宮を、何日も、あるいは何年も彷徨い続けたような感覚があった。時間の概念は融解し、私は永遠にこの鮮やかすぎる牢獄から出られないのだと諦めかけていた。
ある時、夢の中の看護師たちが、影のように音もなく私の周りに集まってきた。 彼女たちの顔にはモザイクがかかったように特徴がなく、目鼻立ちが読み取れない。ただ白い制服だけが、暗闇の中でぼんやりと浮き上がっている。 「これから身体を洗うので、移動しますね」 事務的で、一切の抑揚がない合成音声のような響き。 それは治療というより、まるで厳粛な「儀式」の準備、あるいは廃棄処理の手順のようだった。 私は「待ってくれ」と言う間もなく、冷たい感触のストレッチャーに乗せ換えられた。身体が縛り付けられたように動かない。

ガラガラガラ……。 キャスターが硬い床を転がる音が、それまでの静寂を切り裂くように響き始めた。その音は妙にリアルで、骨に響くような振動を伴っていた。
ストレッチャーは薄暗い廊下を滑るように進んでいく。天井の蛍光灯が、白い流星のように等間隔で視界を流れていく。 背中に伝わる微細な振動と、身体が足の方へ引っ張られる感覚でわかった。 この廊下は、平坦ではない。緩やかだが、確実に続く「下り坂」になっている。
ストレッチャーは重力に従い、加速しながら、どんどん、どんどん、奥へ、下へと運ばれていく。 一度転がり落ちれば二度と這い上がれないような、底なしの傾斜。 行き先は明らかに「地下」だった。
病院の地下。そこにあるのは何だ? 検査室か? 霊安室か? それとも、もっと深い、光の届かない「黄泉の国」への入り口か?
「なんで地下なんだろう……? やめてくれ、下に行きたくない!」
逃げ場のないストレッチャーの上で、漠然とした、しかし芯まで凍えるような冷たい恐怖が胸をよぎる。心拍数が上がり、呼吸が荒くなるのを感じる。私は流れていく天井の無機質な模様を、祈るような気持ちで凝視し続けた。このまま地下に着いてしまえば、もう二度と戻れない。私の魂ごど、あちら側に回収されてしまう。
すると、完璧だった夢の景色に、小さな亀裂が入り始めた。
それまでツルリとして無機質だった夢の中の天井に、小さな「シミ」が見えたのだ。 雨漏りの跡のような、茶色く変色したその一点。その「汚れ」を見つけた瞬間、世界の解像度が歪んだ。
夢特有の柔らかな粒子状の光が、ジジジ……と音を立てるような、古びた蛍光灯の「鋭く、痛い光」へと変質していく。 点滅する光が、私の瞼を強引にこじ開けるように刺激する。
 鼻孔を突く空気が変わる。 無臭で無菌だった極彩色の世界に、ツンとする消毒液の刺激臭と、排泄物や古い建物特有のカビ臭さが混じり始める。むせ返るような「生」と「生活」の臭いだ。
鼻孔を突く空気が変わる。 無臭で無菌だった極彩色の世界に、ツンとする消毒液の刺激臭と、排泄物や古い建物特有のカビ臭さが混じり始める。むせ返るような「生」と「生活」の臭いだ。
極彩色の夢のフィルターが、古くなった壁紙のようにボロボロと剥がれ落ちていく。 それまで感じていた魂の浮遊感が急速に消え失せ、代わりに、身体全体に熱い鉛を流し込まれたような、強烈な重力がのしかかってきた。 全身の筋肉が軋み、関節が悲鳴を上げる。喉の奥にチューブの異物感がある。
地下への入り口だと思っていたその場所は、死の世界ではなく、現世への出口だったのだ。
極彩色の夢が色あせ、モノクロームの、しかし確かな質量を持った空間が露わになる。 冷たく、重く、全身をねじ切られるような痛みを伴う「現実」の物質感が、圧倒的な質量で私に迫ってきた。
 3章に続く。
3章に続く。