
最終章:砕けた器と父の導き
学生生活も無事卒業し新しい生活を始めていた頃。私は自分が「生かされた」本当の理由について、いくつかの衝撃的な事実を知ることになった。
すべての始まりは、退院の手続きを済ませ、最後に執刀医の先生へ挨拶に行った時のことだ。 診察室のドアをノックし、「失礼します」と入っていく。 デスクに向かっていた先生が顔を上げ、私の姿――杖をつきながらも、しっかりと自分の足で歩いている姿――を見た瞬間、目を見開いて声を上げた。
「おおっ! こんなに良くなったんだ!」
先生は椅子から立ち上がりかけ、信じられないものを見るように私をまじまじと見つめた。 「先生、長い間ありがとうございました」 頭を下げる私に、先生は深く頷き、しみじみとした口調で語り始めた。
「いやあ、すごいな……。君ね、今だから言うけど、本当に奇跡的なんだよ」 「奇跡、ですか?」 「ああ。君が運ばれてきた時のこと、鮮明に覚えてるよ。大腿骨(だいたいこつ)の骨折に、骨盤骨折。まさに身体の土台がバラバラの状態だった」
先生はカルテを指差しながら、当時の絶望的な状況を淡々と、しかし熱を込めて説明した。
「あのレベルの多発外傷と出血だ。良くて一生車椅子、悪ければ植物状態、最悪の場合はそのまま……というのが、我々の当初の見立てだったんだ」
背筋が凍りついた。私は単に「骨が折れた」わけではなかったのだ。人生そのものが終わるか、永遠に閉ざされるかの瀬戸際にいたのだ。 先生は私の目を真っ直ぐ見て言った。
「ここは緊急病棟だ。毎日、瀕死の患者さんが運ばれてくるけれど、その多くは悲しい結果になったり、意識が戻らないまま療養型の病院へ転院していったりする。ここから『自分の足で歩いて』日常へ帰っていく患者を見送ることなんて、滅多にないんだよ」
先生の瞳が少し潤んでいるように見えた。それは、数えきれないほどの「死」や「後遺症」を見てきた医師だからこそ感じる、偽りのない喜びだった。
「だからね、君みたいにこうして回復して、玄関から送り出せることが……医者として、本当に嬉しいんだよ。よく頑張ったね」
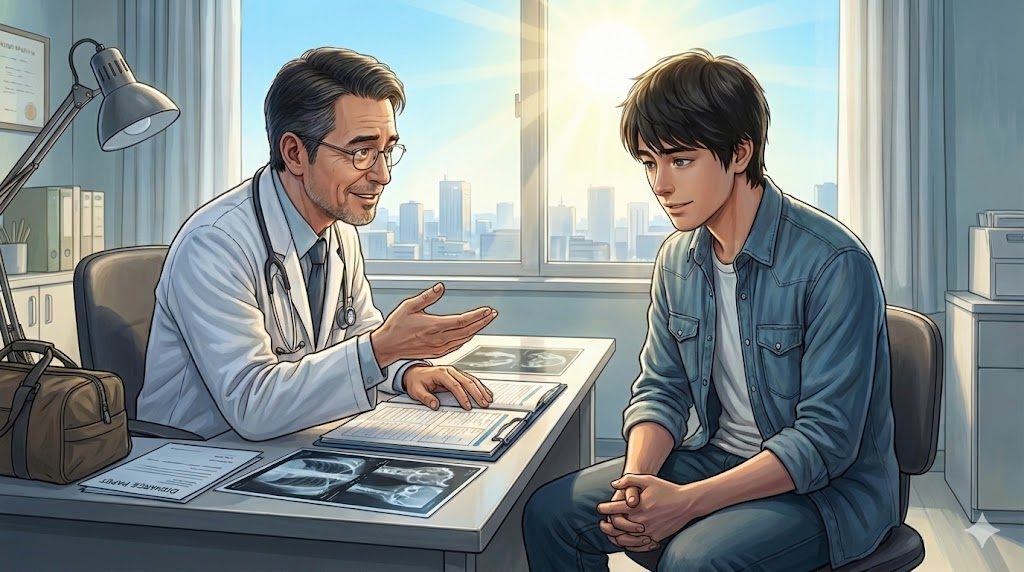 その言葉を聞いた時、私は初めて、自分がどれほど薄い氷の上を歩いて生還したのかを理解した。 大腿骨と骨盤という、人間が立つための主要な骨が砕け散りながら、今こうして立っている。 それは、医学のプロが「奇跡」と呼ぶレベルの現象であり、単なる偶然や若さだけで説明がつくものではなかった。 私は、何かに強烈に守られていたのだ。
その言葉を聞いた時、私は初めて、自分がどれほど薄い氷の上を歩いて生還したのかを理解した。 大腿骨と骨盤という、人間が立つための主要な骨が砕け散りながら、今こうして立っている。 それは、医学のプロが「奇跡」と呼ぶレベルの現象であり、単なる偶然や若さだけで説明がつくものではなかった。 私は、何かに強烈に守られていたのだ。
その日を境に、パズルのピースが埋まるように、私を守ったいくつかの「見えない力」の存在が明らかになった。
1つ目は、母から聞いた話だ。 あの日、私が事故を起こしたまさにその時刻。 母は働いていた飲食店での出来事。厨房で、具材を入れるための分厚い業務用の陶器を用意していた時だ。 誰も触れていない。地震も起きていない。それなのに、その頑丈な器が突然、 「パリーン!!」 と鋭い音を立てて、真っ二つに割れたのだという。
 「あんな割れ方、見たことなかったよ……」 母は強烈な胸騒ぎを覚え、その直後に病院からの電話が鳴ったそうだ。 今にして思えば、あの器が私の「身代わり」となって砕け散ってくれたのかもしれない。私の頭蓋骨や心臓が割れる代わりに、その衝撃を一身に引き受けて。
「あんな割れ方、見たことなかったよ……」 母は強烈な胸騒ぎを覚え、その直後に病院からの電話が鳴ったそうだ。 今にして思えば、あの器が私の「身代わり」となって砕け散ってくれたのかもしれない。私の頭蓋骨や心臓が割れる代わりに、その衝撃を一身に引き受けて。
2つ目は、事故現場での真実だ。 あの日、スローモーションの世界で転倒し、意識が遠のく中で声をかけてくれた「誰か」のこと。 後になって知ったが、彼はただの通行人や野次馬ではなかった。 たまたま通りかかった「消防士」だったのだ。
彼は現場の惨状を見て瞬時に状況を判断し、救急車が到着するまでの数分間、的確な止血処置と応急処置を行ってくれていたという。 もし彼がその道を通らず、ただの親切な素人が対応していたら。あるいは発見が数分遅れていたら。 医師の言う通り、私は病院に着く前に命を落としていたか、脳に酸素がいかず植物状態になっていただろう。 あの時感じた「温かい掌(てのひら)」は、プロフェッショナルの救命の手だったのだ。
 そして最後の一つ。これが私にとって最も大きな衝撃だった。 ある日、私は自分が事故を起こした現場を改めて地図で確認し、息を飲んだ。
そして最後の一つ。これが私にとって最も大きな衝撃だった。 ある日、私は自分が事故を起こした現場を改めて地図で確認し、息を飲んだ。
緩やかな左カーブ。私が曲がりきれずに転倒した、あの場所。 そのカーブの延長線上、私の身体が投げ出された視線の先に何があるか、気づいてしまったのだ。
そこには、かつて私の父が息を引き取った病院があった。 もっと言えば、父が最期を迎えた病室の窓がある方角を、そのカーブは見下ろしていたのだ。
あそこで私が死にかけたのは、父に呼ばれたからだろうか? 「寂しいからこっちに来い」と、引き寄せられたのだろうか?
いや、違う。絶対に違うと確信した。 あの極彩色の夢の中で、地下へ連れて行かれそうになった私を、強烈な不快感と痛みで現実へと押し戻した力。 それはきっと、父が「お前はまだこっちに来るな!」と、あのカーブの手前で仁王立ちになり、あの世への入り口で立ちふさがってくれたからではないだろうか。 父は私を呼んだのではない。私が境界線を越えそうになった瞬間、魂を蹴飛ばしてでも現世に突き返してくれたのだ。
 身代わりになって砕けた母の器。 絶妙なタイミングで命を繋いでくれた消防士の手。 そして、あのカーブで「門番」として私を守ってくれた父。 そして何より、ここから歩いて帰ることを心から喜んでくれた医師たちの尽力。
身代わりになって砕けた母の器。 絶妙なタイミングで命を繋いでくれた消防士の手。 そして、あのカーブで「門番」として私を守ってくれた父。 そして何より、ここから歩いて帰ることを心から喜んでくれた医師たちの尽力。
多くの「見えない力」と、現実の人々の「必死の努力」が幾重にも重なり合って、私の命はギリギリのところで繋ぎ止められたのだ。
鏡を見る。 痩せて筋肉が落ちた身体。右足に残る大きな手術痕。骨盤を貫いていたボルトの穴の跡。 以前の私なら、この傷だらけの身体を嘆いただろう。 だが今は違う。 失われた筋肉も、移植痕の残るお尻も、不格好な傷跡も、すべては私が「死の淵」から這い上がってきた証であり、勲章だ。
空白になった夏と引き換えに、私は「生かされた命」の重みを知った。 ただ歩けること。息ができること。痛いと感じること。そのすべてが、どれほどの奇跡の上に成り立っているかを知った。
窓の外では、また新しい夏が始まろうとしている。 セミの声が聞こえる。アスファルトが焼ける匂いがする。 私はこの継ぎ接ぎの足で、しっかりと地面を踏みしめる。 「行ってきます」 誰にともなく呟き、私は私の人生を、一歩ずつ歩き出した。
 完。
完。


