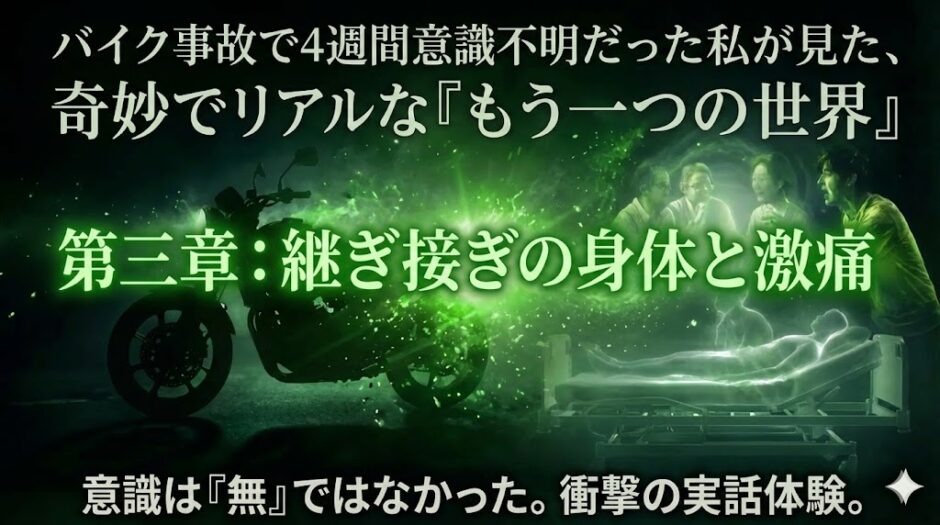鉛のように重い瞼を、全神経を集中させてゆっくりと持ち上げた。 視界に白い光が差し込む。ぼやけた輪郭が徐々に焦点を結び、無機質な天井のシミが浮かび上がった。 ピ、ピ、ピ……という電子音。鼻孔を刺す消毒液の冷たい匂い。
鉛のように重い瞼を、全神経を集中させてゆっくりと持ち上げた。 視界に白い光が差し込む。ぼやけた輪郭が徐々に焦点を結び、無機質な天井のシミが浮かび上がった。 ピ、ピ、ピ……という電子音。鼻孔を刺す消毒液の冷たい匂い。
「……あ、目覚めた!」「先生呼んで! 意識戻りました!」
遠くで聞こえていたざわめきが、急激にボリュームを上げて耳に飛び込んでくる。看護師たちが慌ただしく駆け回る足音が、床を振動させて鼓膜を揺らす。 私はまだ、長い昼寝から無理やり起こされたような、あるいはまだあの極彩色の夢の続きにいるような、現実感のない浮遊の中にいた。
 しかし、その浮遊感はすぐに、圧倒的な「重力」と「違和感」にかき消された。
しかし、その浮遊感はすぐに、圧倒的な「重力」と「違和感」にかき消された。
身体が動かない。指一本動かすのにも、全身のエネルギーが必要なほど重い。そして何より、下腹部に感じる異様な感触――まるで身体の内側から杭を打たれたような、重苦しい圧迫感があった。 恐る恐る布団をめくり、自分の腰のあたりに目をやった瞬間、私は息を飲んだ。思考が凍りついた。
「なんだ……これ……」
そこにあったのは、かつての健康な高校生の身体ではなかった。 骨盤の皮膚を突き破り、左右から太い金属のボルトが突き出している。さらに、それらを繋ぐ金属のフレームが、まるで工事現場の足場のように私の下半身を覆っていた。 体内で粉砕した骨盤を無理やり固定するための「創外固定器」。
生身の肉体に、冷たく無機質な金属が直接融合している。その光景はあまりにグロテスクで、自分自身がフランケンシュタインか、実験に失敗したサイボーグに改造されたようだった。ボルトが刺さっている皮膚の境界線が赤黒く腫れ、そこが自分の身体であることを生々しく主張していた。
そして、右足の惨状はさらに筆舌に尽くしがたいものだった。 包帯の下にあるその足は、見るも無残な状態だった。後から聞いた話だが、事故直後、私の右足は肉が大きく裂け、白い骨が露出するほどの重傷だったらしい。 失われた皮膚と肉を補うため、私の身体は「継ぎ接ぎ」になっていた。 右足首の皮膚を剥がし、さらにお尻の皮膚も剥がして、損傷の激しい部分へ移植する手術が行われていたのだ。右足には、別の場所から持ってきた皮膚がパッチワークのように張り合わされ、皮膚の色も質感もまばらな、不格好な地図を描いていた。
窓の外では、高校最後の夏休みが輝いているはずだ。クラスメイトたちは受験勉強に励んだり、最後の思い出を作ったりして、未来に向かって着実に時を進めているだろう。 しかし、ここだけは完全に時間が止まっている。世界から切り離された真っ白な病室で、私はたった一人、置き去りにされた焦燥感と、自分の壊れた身体に向き合うしかなかった。
 激痛や金属の異物感と同じくらい、あるいはそれ以上に私の心をへし折ったのは、「排泄」という生理現象に伴う尊厳の喪失だった。 骨盤を固定され、ベッドから一歩も動けない私は、トイレに行くことすら許されない。尿道には、意識がない間にカテーテルという管が直接挿入されていた。 膀胱に異物が入っている強烈な違和感。自分の意思とは無関係に、管を通して排泄物が袋へと流れていく感覚。
激痛や金属の異物感と同じくらい、あるいはそれ以上に私の心をへし折ったのは、「排泄」という生理現象に伴う尊厳の喪失だった。 骨盤を固定され、ベッドから一歩も動けない私は、トイレに行くことすら許されない。尿道には、意識がない間にカテーテルという管が直接挿入されていた。 膀胱に異物が入っている強烈な違和感。自分の意思とは無関係に、管を通して排泄物が袋へと流れていく感覚。
「管、チェックしますねー」
若い女性の看護師が布団をめくり、淡々と処理をしていく。羞恥心で顔から火が出るなんて生易しいものではない。18歳の男としてのプライドが、音を立てて崩れ落ちていく。ただ怪我をしただけなのに、私は人間としての自立すら奪われていたのだ。
そこから、地獄のようなリハビリの日々が始まった。 まず驚愕したのは、自分の変貌ぶりだ。ベッドの上で身体を起こそうとするだけで、世界が回るほどの目眩に襲われる。体重は20キロも落ちていた。 ふと鏡に映った自分を見た時、言葉を失った。
そこにいたのは私ではなく、飢餓に苦しむ老人のような姿だった。
中学時代、部活動で来る日も来る日もコートを走り回り、泥のように眠る日々の中で培った筋肉。毎日のフットワークと走り込みで鋼のように硬く、太くなっていた太ももやふくらはぎ。それは私の自尊心の一部でもあった。 しかし、それらが嘘のように消え失せている。筋肉も脂肪もすべて削ぎ落とされ、骸骨に薄い皮を被せたようにあばら骨が浮き出し、自慢だった脚は枯れ木のように細くなっていた。
 「あの時のあんた、何もわかってない顔で天井を見上げて、まるで生まれたての赤ん坊に戻ったみたいだったよ」
「あの時のあんた、何もわかってない顔で天井を見上げて、まるで生まれたての赤ん坊に戻ったみたいだったよ」
後に母が語った言葉が、痛烈な現実味を帯びて蘇る。 筋肉という鎧を剥がされ、排泄さえも自分ではできず、ただ弱々しく横たわるその姿。私は文字通り、無力な「赤ん坊」に逆戻りしていたのだ。
さらに私を恐怖させたのは、身体だけでなく、「脳」の機能までもが完全ではないことだった。 リハビリの一環でペンを持たされた時のことだ。「自分の名前を書いてみて」と言われ、簡単なことだと思いペンを握ろうとした。しかし、手が震えて力がさらに入らない。脳では明確に「書け」と命令しているのに、指先への信号が途中で断線しているかのように、全く連動しないのだ。 白い紙の上で、ペン先が迷子のように震える。ミミズが這ったような線を引くのがやっとで、自分の名前の漢字はおろか、ひらがなさえ思い出せない瞬間があった。
 (あのハンマーで殴られたような衝撃で、脳の回路まで焼き切れてしまったのか?)
(あのハンマーで殴られたような衝撃で、脳の回路まで焼き切れてしまったのか?)
肉体的な損傷以上に、自分という人間を形成する司令塔が破壊されてしまったかもしれない恐怖。それは痛みとは違う、底なしの冷たい汗となって背中を伝った。私は、言葉も、文字も、動きも、すべてゼロから覚え直さなければならなかった。
そして、肉体的な苦痛において最も過酷だったのが「座る」ことだ。 本来、休息の姿勢であるはずの「座る」という行為が、私にとっては拷問そのものだった。脂肪が落ちて骨と皮だけになったお尻。そこは、移植手術のために皮膚を大きく切り取られた「ドナー採取部」でもあった。皮膚は薄く、神経が過敏になっている。 リハビリ室の椅子に座ろうとする。座面が硬いわけではない。クッション性のある柔らかい椅子でさえ、私には剣山のように感じられた。薄くなった皮膚と筋肉を通して、尖った坐骨(ざこつ)がダイレクトに座面に突き刺さる。自分の体重そのものが凶器となり、剥き出しの神経と骨を圧迫するのだ。
「ぐっ……!!」
脂汗が噴き出るほどの激痛。焼けるような痺れと、骨が軋む感触。 どんなに柔らかい椅子であっても、座っているだけで脂汗が止まらず、歯を食いしばるあまり顎が痛くなる。痛みで思考が真っ白になる中、私は数秒座っては倒れ込むことを繰り返した。
 さらに、右足にはもう一つの試練が待ち受けていた。 度重なる手術と長期間の固定により、右足の関節や筋肉がコンクリートのようにガチガチに固まってしまっていたのだ。膝を曲げようとしても、まるで錆びついた蝶番のようにロックがかかって、ある一定の角度からびくともしない。 「正座」なんて、夢のまた夢だった。それでも、元の機能を取り戻すためには、固まった関節をこじ開けるしかない。 理学療法士の先生と共に、凝り固まった筋肉を無理やり引き伸ばし、癒着した組織をベリベリと剥がしていくような地道なリハビリが続いた。
さらに、右足にはもう一つの試練が待ち受けていた。 度重なる手術と長期間の固定により、右足の関節や筋肉がコンクリートのようにガチガチに固まってしまっていたのだ。膝を曲げようとしても、まるで錆びついた蝶番のようにロックがかかって、ある一定の角度からびくともしない。 「正座」なんて、夢のまた夢だった。それでも、元の機能を取り戻すためには、固まった関節をこじ開けるしかない。 理学療法士の先生と共に、凝り固まった筋肉を無理やり引き伸ばし、癒着した組織をベリベリと剥がしていくような地道なリハビリが続いた。
「いきますよ。息を吐いて」 「ぐ、うぅぅぅぅッ!!」
骨が軋み、筋肉が悲鳴を上げる。 涙と鼻水で顔をぐしゃぐしゃにしながら、私は必死に痛みに耐えた。
かつての強靭な肉体も、プライドも、尊厳も、すべて失った。 私は文字通り、何もできない「無力な赤ん坊」に逆戻りしたのだ。
ならば、ここからやり直すしかない。 筋肉を削ぎ落とし、骨を砕き、皮膚を貼り直して作られた、この新しい「継ぎ接ぎの身体」で。。。
 4章につづく。
4章につづく。