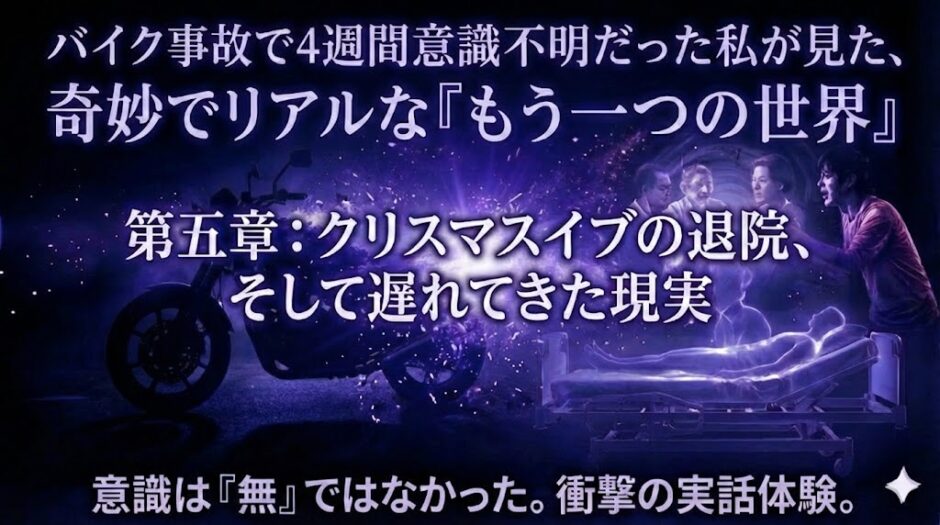第五章:クリスマスイブの退院、そして遅れてきた現実
病院の自動ドアが開いた瞬間、私の頬を刺したのは、驚くほど冷たく澄んだ冬の風だった。
退院の日は、12月24日。 世間がクリスマスイブに浮き足立つ、一年で最も華やかな日だった。
8月の真夏の夜、アスファルトの熱気とサイレンの音の中で救急搬送されてから、およそ4ヶ月。
季節は夏から秋を通り越し、完全に冬になっていた。
街路樹は葉を落とし、街は煌びやかなイルミネーションで彩られている。
浦島太郎という言葉があるが、まさにその心境だった。
私だけが、あの夏の夜から時間が止まったまま、いきなり未来へと放り出されたようだった。
 家に帰って最初に直面したのは、「家」という空間の不自由さだった。
家に帰って最初に直面したのは、「家」という空間の不自由さだった。
バリアフリーだった病院とは違い、築年数の経った我が家は段差だらけだ。
玄関の上がり框(かまち)ひとつ越えるのに、脂汗をかいて杖をつく。
2階の自分の部屋に行くための階段は、まるでアルプス登山のような険しい壁に見えた。
手すりにしがみつき、一段一段、這うように登る。 風呂に入るのも一苦労だ。
浴槽をまたぐ筋力がないため、まるで老人のようにへっぴり腰で時間をかけて浸かるしかない。
年が明け、1月。 いよいよ、私が「日常」である学校に戻る時が来た。
2学期を丸ごと欠席していたため、出席日数が足りず、結論はすでに「留年」と決まっていた。
かつての同級生たちが、大学受験や卒業に向かってラストスパートをかけている中、私だけがスタートラインに戻される。
復学初日。私は久しぶりに電車に乗るため、駅の券売機の前に立った。 そこで、自分の身体に起きている「深刻なエラー」を突きつけられた。
目的地の運賃は「150円」。 頭では分かっている。目でも「150」のボタンを捉えている。 「ここを押せ」と脳が指令を出し、人差し指を伸ばした。 しかし、私の指は、まるで何かに弾かれたように勝手に軌道を変え、隣にある「300円」のボタンを押そうとしたのだ。
「え……?」
 慌てて手を引っ込める。もう一度、慎重に狙いを定める。150円、150円……。
慌てて手を引っ込める。もう一度、慎重に狙いを定める。150円、150円……。
けれど、指先がボタンに近づくにつれて震え出し、どうしても狙った場所に着地しない。
磁石の同じ極同士が反発するように、指が逃げていく。 脳のイメージと、実際の身体の動きが完全にズレている。 (俺の脳みそ、やっぱり壊れてるのか……?)
背筋が凍るような恐怖を感じながら、私は震える手で、時間をかけてなんとか切符を買った。
改札を通るだけで、私はひどく消耗していた。
 教室に着くと、クラスメイトたちは温かく迎えてくれた。「おかえり!」「痩せたな!」という歓声。
教室に着くと、クラスメイトたちは温かく迎えてくれた。「おかえり!」「痩せたな!」という歓声。
しかし、温かい輪の中にいながらも、私は同時に決定的な「ズレ」を感じていた。 時期は3学期。
友人たちは「センター試験」や「大学」といった未来の話をしているが、私だけが「過去」の怪我と向き合っている。 笑顔で話しながらも、透明なガラス一枚隔てられたような孤独。
そして3月。私は卒業式を欠席し、静かに「同級生たちとの別れ」を通過させた。
4月。校庭の桜が咲き、私は「二度目の高校3年生」を始めた。 新しいクラスメイトは全員、一つ下の年下たちだ。 最初は「ダブりの先輩」として浮かないよう、自分から「敬語なしでいいよ」と声をかけ、溶け込む努力をした。 その甲斐あってクラスには馴染めたが、ある日の体育の授業で、私は再び絶望を味わうことになった。
種目はバスケットボール。 見学することもできたが、私は「少しなら動けるかもしれない」という淡い期待を抱いて参加した。
練習メニューは「レイアップシュート」。列に並び、順番にドリブルしてシュートを打つ。 中学時代、バスケ部だった私にとっては、呼吸をするより簡単な動作のはずだった。
 私の番が来た。 (右、左、ジャンプして、置いてくる) 頭の中のイメージは完璧だ。NBA選手のようにスムーズな動きが再生されている。 私はボールを受け取り、走り出した。
私の番が来た。 (右、左、ジャンプして、置いてくる) 頭の中のイメージは完璧だ。NBA選手のようにスムーズな動きが再生されている。 私はボールを受け取り、走り出した。
――その瞬間、世界が崩れた。
一歩目の足が出ない。ボールをつくリズムと足の運びがバラバラだ。 「あれ?」と思った時にはもう遅い。 脳内では華麗にジャンプしているはずのタイミングで、実際の身体は重りのように地面にへばりつき、足がもつれた。 手と足がまるで他人のもののように勝手に暴れる。 「うわっ!」 私は無様にバランスを崩し、シュートを打つどころか、ボールをあらぬ方向へ放り投げて転びそうになった。
「……あ」
ボールが虚しく床を転がる。 シン……と静まり返る体育館。 イメージしていた「自分」と、現実に動いた「壊れた身体」。そのあまりの落差に、私は立ち尽くした。 かつて自信を持っていた運動神経も、身体感覚も、すべて事故の衝撃でリセットされてしまったのだ。
「ドンマイ! 次いこう!」 気を使った新しいクラスメイトの声が、逆に胸に刺さった。
私は苦笑いで誤魔化しながら、列の最後尾に戻ることもできず、すごすごと見学席へと下がった。
(もう、戻れないんだな) 悔しさよりも、深い喪失感が私を包んだ。けれど、その強烈な「失敗」のおかげで、私は過去の自分とは決別し、今の不格好な自分を受け入れる覚悟が決まったような気がした。
 そんな私の心の支えになったのは、かつての担任の先生の存在だ。 先生は人事異動で中等部の担当になり、別の校舎にいた。私は足のリハビリがてら、定期的に長い廊下を歩いてその棟まで足を運び、近況を報告しに行った。 「足の調子はどうだ?」「勉強遅れてないか?」 先生は私の「空白の時間」や「脳と身体のズレ」を知る数少ない理解者として、常に見守ってくれていた。
そんな私の心の支えになったのは、かつての担任の先生の存在だ。 先生は人事異動で中等部の担当になり、別の校舎にいた。私は足のリハビリがてら、定期的に長い廊下を歩いてその棟まで足を運び、近況を報告しに行った。 「足の調子はどうだ?」「勉強遅れてないか?」 先生は私の「空白の時間」や「脳と身体のズレ」を知る数少ない理解者として、常に見守ってくれていた。
そして1年後。 私はようやく、本当の卒業式を迎えた。
体育館の床の冷たさが、パイプ椅子を通して伝わってくる。 去年は逃げ出したこの場所に、私は今、座っている。 厳粛な空気の中、担任の声が響いた。私の名前だ。
「はい!」
静まり返った体育館に、私の声が響く。震えはなかった。 パイプ椅子から立ち上がる。右足に体重を乗せる。ボルトが抜かれた骨は、もう悲鳴を上げない。 一歩、また一歩。 壇上へと続く階段を登る。 かつては当たり前のように駆け上がれた段差が、今はとても高く、神聖なものに感じられた。 校長先生の前まで歩みを進め、一礼する。 手渡された卒業証書の筒。 それは、ただの紙切れが入った筒とは思えないほど、ずっしりと重かった。 この重みの中に、失われた筋肉も、流した脂汗も、孤独な夜も、すべてが詰まっている気がした。 壇上から降りて、席に戻るまでの景色は、涙で少し滲んで見えた。
 式が終わり、喧騒が落ち着いた頃、私はお世話になったあの中等部の先生のもとへ挨拶に行った。
式が終わり、喧騒が落ち着いた頃、私はお世話になったあの中等部の先生のもとへ挨拶に行った。
春の陽射しが差し込む職員室の入り口。 先生は私の顔を真っ直ぐ見て、短く、しかし万感の思いを込めてこう言ってくれた。
「よく頑張ったな」
その一言が、私の胸に深く染み渡った。 バイク事故で死にかけ、脳と身体の自由を奪われ、留年という回り道を経て、ようやく辿り着いたゴール。 遠回りをした。多くのものを失った。 だが、その分、私は人の温かさと、ただ歩き、ただ笑い、当たり前の明日が来ることの尊さを、誰よりも深く学ぶことができた。 不自由な指先も、思うように動かない足も、すべて私が生きてここに在る証だった。
 最終章へ続く。
最終章へ続く。