第四章:骨に響く振動と、軋む身体
「奇跡的に助かった」 周囲はそう言ったし、私自身もそう思っていた。だが、その代償はあまりにも大きく、支払いはまだ終わっていなかった。
私の身体には、まだ異物が埋まっていた。 砕けた骨盤をパズルのように繋ぎ止めるための、太く長い金属製のボルトだ。 これを取り除く手術、いわゆる「抜釘(ばってい)手術」は2段階に分かれていた。 最初は、身体の外に飛び出しているジャングルジムのような固定具(創外固定器)の除去。これは全身麻酔で行われたため、私は深い眠りの中で、気づけば身軽になっていた。
問題は、その数ヶ月後に行われた2回目の手術だ。 今度は、皮膚の下、骨の髄深くに埋め込まれているボルトを直接引き抜く手術になる。 術前の説明室で、レントゲン写真を指差しながら医師はさらりと告げた。 「今回の手術は、下半身だけの部分麻酔で行いますね」 私は耳を疑った。 「全身麻酔じゃないんですか? ……意識がある状態でやるんですか?」 「短期間で全身麻酔を繰り返すのは、身体への負担が大きすぎるんだよ。君は事故で20キロも痩せてしまって、体力もまだ戻りきっていない。呼吸器系へのリスクを避けるためにも、今回は局所麻酔でやらせてほしい」
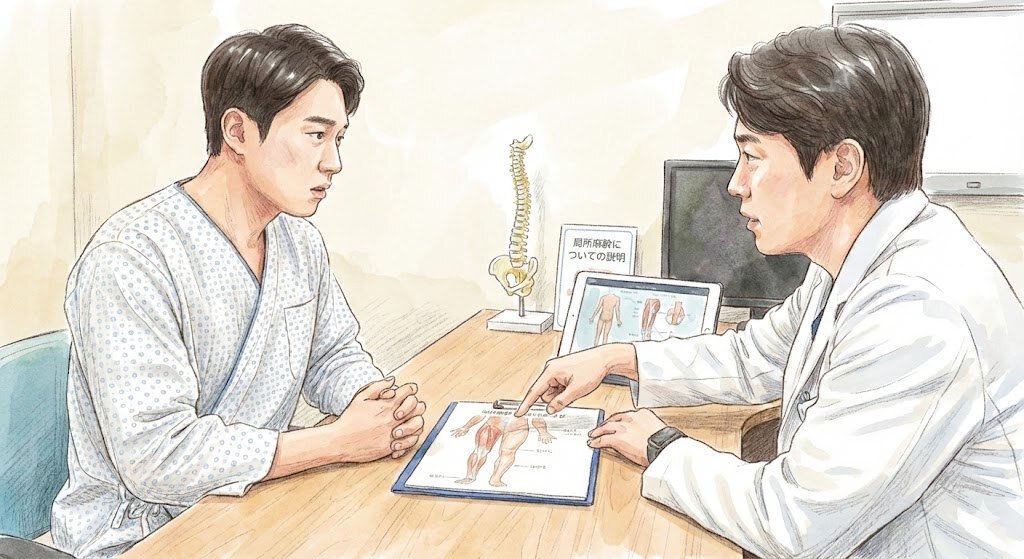 医師の言葉は医学的に正論だった。反論の余地はない。しかし、「自分の身体が切り開かれ、骨から金属が抜かれる音を聞き続ける」という恐怖は、想像するだけで胃液がせり上がってくるようだった。
医師の言葉は医学的に正論だった。反論の余地はない。しかし、「自分の身体が切り開かれ、骨から金属が抜かれる音を聞き続ける」という恐怖は、想像するだけで胃液がせり上がってくるようだった。
手術当日。 冷え冷えとした手術室の空気。無影灯の白すぎる光。 手術台の上で、私の意識は恐ろしいほど鮮明だった。 背中に注射を打たれると、すぐに下半身が温かくなり、やがて鉛のように重くなった。医師がピンセットで太ももをつねる。 「痛くないかい?」 「……はい。触られているのは分かりますけど、痛みはないです」 感覚はあるのに、痛みだけが消えている。自分の足が、肉屋の店先に吊るされたただの肉塊になったような、奇妙な分離感があった。
(これなら、大丈夫かもしれない) 目の前にかけられた緑色の布(ドレープ)の向こうで、ガチャガチャと金属音がし始める。皮膚が切開されているはずだが、何も感じない。 私は高をくくっていた。所詮はネジを抜くだけだ、と。 だが、その安堵は、医師がボルトの頭に「レンチ」のような器具を嵌め込んだ瞬間に打ち砕かれた。
医師の手が動き、錆びついたボルトが回される。
ゴリッ、ゴリッ、ゴリゴリゴリ……!!
「!!?」
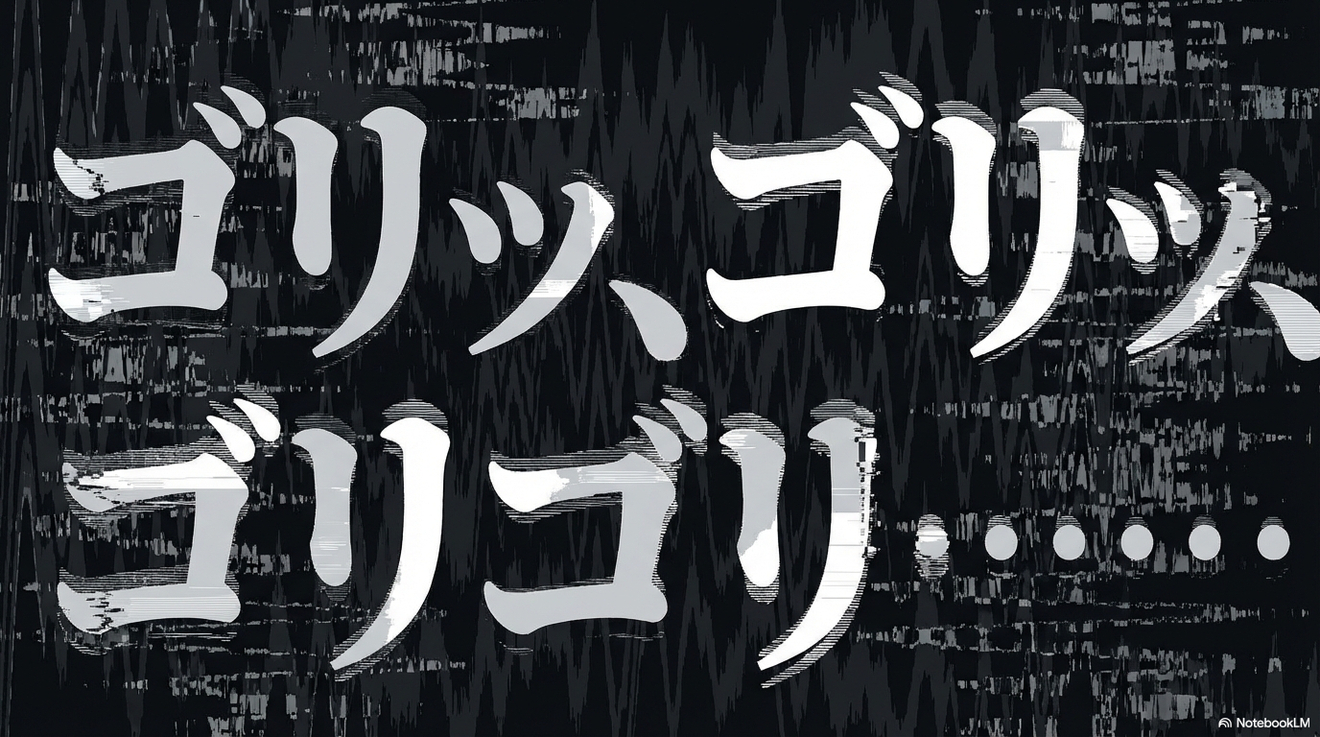 痛みという言葉では表現できない、もっと根源的な恐怖が身体を駆け巡った。 皮膚や肉の痛みはない。麻酔は完璧に効いている。 しかし、骨は別だった。 ボルトが骨の組織を削りながら回る摩擦、金属と骨が擦れ合う鈍く重い振動。 それらが、骨盤から背骨という「身体の大黒柱」を伝導し、脊髄を駆け上がり、頭蓋骨にダイレクトに響いてくるのだ。
痛みという言葉では表現できない、もっと根源的な恐怖が身体を駆け巡った。 皮膚や肉の痛みはない。麻酔は完璧に効いている。 しかし、骨は別だった。 ボルトが骨の組織を削りながら回る摩擦、金属と骨が擦れ合う鈍く重い振動。 それらが、骨盤から背骨という「身体の大黒柱」を伝導し、脊髄を駆け上がり、頭蓋骨にダイレクトに響いてくるのだ。
耳から聞こえる音ではない。身体の内側、脳の芯から直接鳴り響く、不快極まりない轟音。 まるで、自分の身体が工事現場になったかのようだった。 頭の中で道路工事のドリルが暴れている。あるいは、巨大な臼歯を麻酔なしで引っこ抜かれているような感覚。 そのあまりに強烈な「振動」は、脳内で誤変換され、耐え難い「激痛」となって知覚された。
さらに私を追い詰めたのは、医師たちがかける「力」の凄まじさだった。 長期間埋め込まれていたボルトは、骨と完全に馴染んでしまっているのか、容易には回らないようだった。 医師が体重をかけてレンチを回すたびに、私の身体は手術台の上で揺さぶられた。
「ぐっ……うぅ……!」
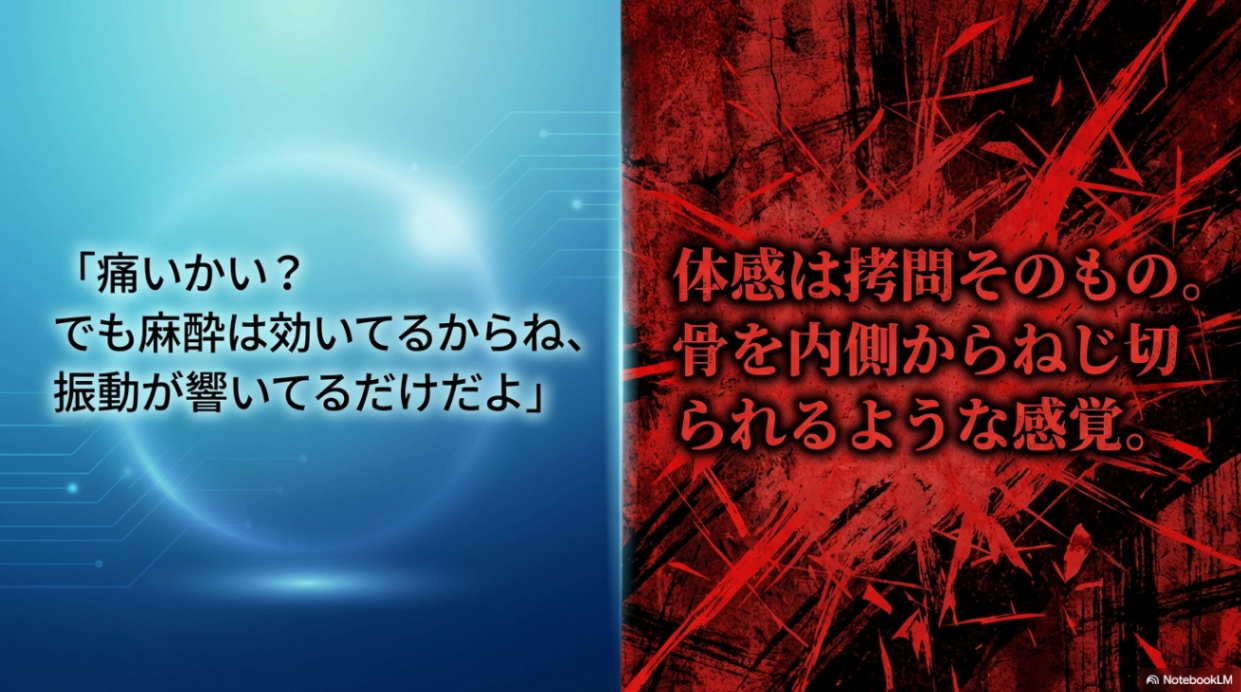 麻酔で動かないはずの下半身が、物理的な力でぐいぐいと左右に持っていかれる。 私が台から落ちないように、助手の看護師たちが私の肩や胸を上から押さえる。
麻酔で動かないはずの下半身が、物理的な力でぐいぐいと左右に持っていかれる。 私が台から落ちないように、助手の看護師たちが私の肩や胸を上から押さえる。
(嘘だろ……そんなに力を入れるのか……!)
ボルトが回るたびに、ギシギシと骨がきしむような鈍い音が頭蓋骨に響く。 まるで錆びついた機械を無理やり分解しているような感覚。 医師たちは淡々と作業を進めているが、私にとっては永遠にも感じる時間だった。聞こえるのは、荒くなった自分の呼吸音と、心電図の冷たい電子音、そして身体の奥底から響く振動だけ。
ここには共有できる痛みはない。私はまな板の上の鯉であり、修理されるのを待つだけの存在なのだ。 一本抜くのに、どれだけの時間がかかるのか。 私は手術台の縁を白くなるほど強く握りしめ、全身から滝のような脂汗を流した。 意識が鮮明な分、恐怖が増幅されていく。 奥歯を食いしばり、必死に天井の模様を見つめて気を逸らそうとした。そうでもしなければ、大声で「やめてくれ」と叫んでしまいそうだった。
カラン。
不意に、重たい金属音がトレイに響いた。 それまでの轟音と圧力が嘘のように止み、私の身体から異物が離れたことを告げる乾いた音。 私は魂が抜けたように脱力した。
「はい、抜けたよ。お疲れ様」
医師の声が遠くに聞こえる。 手術室の天井を見上げながら、荒い息をつく。押さえつけられていた肩の力がようやく抜けた。 骨に空いた穴。そこを風が吹き抜けるような、奇妙にスースーする空虚な感覚だけが残っていた。 この骨に響いた激痛と振動こそが、私が「死ななかった」ことの証明であり、あのスピードの代償として支払うべき、あまりに重い対価だったのかもしれない。
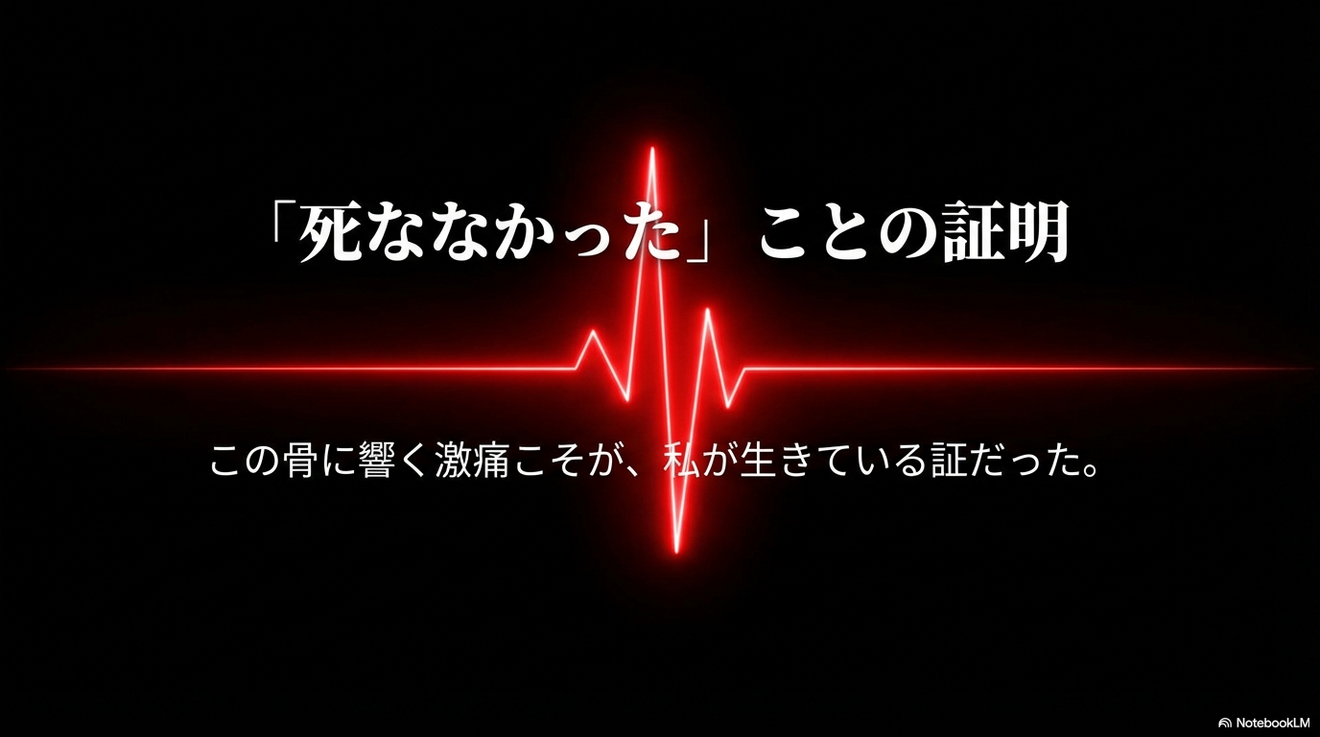 5章へ続く
5章へ続く



